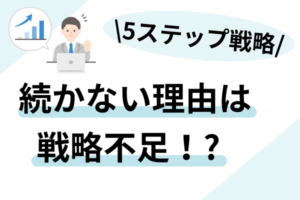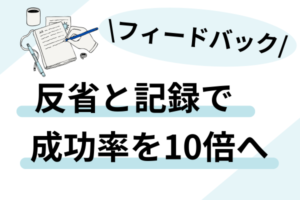習慣が続かない理由は環境にあり!人の力で継続率を3倍アップする方法
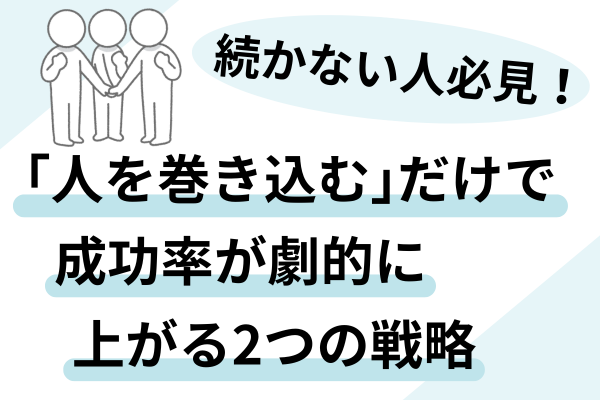
この記事で学べる内容
「また三日坊主で終わってしまった...」
「今度こそは習慣化できると思ったのに」
そんな経験、ありませんか?
私も長年、この繰り返しでした。読書、筋トレ、早起き...数え切れないほどの習慣に挑戦しては挫折し、「自分は継続力が低いな」と自分を責める日々。
しかし、ある発見が私の人生を変えました。それは「習慣化は一人で頑張るものではない」という真実です。
習慣化の成功率を劇的に上げる秘訣。それは「人の力」を活用することです。
良くも悪くも人生を変えるのは「人」。この言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。習慣化においても、この原理は驚くほど効果を発揮します。
今回は、人の力を借りて習慣化を成功させる戦略をご紹介します。
- 習慣化における「人の力」の重要性
- 周りの人で習慣が決まる!?
- 誰でも実践できる「監視効果」を活用した習慣化テクニック
- 「人のため」に行動することで自然とやる気が湧く心理メカニズム
人は周りに影響される生き物
人間は周りの人に影響される生き物です。
「周りの5人の年収の平均になる」というのは有名な話ですが、これは年収だけでなく、すべての習慣に当てはまります。
よくお酒を飲み、揚げ物を食べるグループに属していれば、ダイエットは難しいでしょう。 放課後にゲームセンターに行ったり、フードコートで騒ぐようなグループにいると、勉強を続けるのは困難です。
まずは属すグループを見直す必要があります。
当たり前のレベルを上げてくれる集団に属しただけで、自分自身を成長させることができるのです。
- 挨拶するのが当たり前のグループにいたら、挨拶が出来るようになる。
- 感謝を大切にする文化のグループにいたら、自然と感謝の言葉がたくさん出てくるようになる。
- 周りがみんな早起きしていたら、自分も早起きするようになる。
こんな風に、人は周りの風潮・文化に良くも悪くも流されます。これを「同調圧力」と言います。
変わりたかったら、習慣を変えるしかありません。そして環境を変えると、習慣を一撃で変えることができるのです。
少し厳しいことを言いますが、変わりたかったら、これまでの人付き合いを見直す必要があります。絶交しろと言っているわけではないですが、少し距離を置いて、より自分が求めるものを達成しやすい環境に身を置くことが不可欠です。
習慣化における「人の力」の威力
心理学の研究では、社会的なサポートがある場合の習慣継続率は、一人で取り組む場合と比べて約2倍高いことが示されています。
また、行動経済学の研究によると、「他者に宣言すること」をした人の目標達成率は、そうでない人の約3倍であることが分かっています。
これらの研究が示すのは、「人の力」を活用することは、単なる精神論ではなく、効果が証明された手法だということです。
これからは、習慣化に「人の力」を活用する2つの戦略を解説します。あなたの習慣に取り入れられないか、考えながら読んでみてください!

戦略1:誰かに監視してもらう
間接的な監視効果とは
「監視してもらう」といっても、「私の習慣をチェックしてください!」と直接お願いするわけではありません。ポイントは、間接的に監視されている感覚を作り出すことです。
具体的な実践方法
家族への宣言
「今月から毎日読書するよ!」と家族に宣言してみましょう。たったこれだけで、驚くほど行動が変わります。
なぜなら、人は宣言した手前「やらなければいけない」という心理が働くからです。リビングでスマホをいじっていると、家族の視線が気になって「あ、読書しなきゃ」と自然と本に手が伸びるようになります。
家族が何も言わなくても、心の中で「あれ?今日は本読まないの?」と思われている気がして、なんとなく落ち着かなくなる。この微妙な居心地の悪さが、実は習慣継続の強力な味方になってくれるのです。
SNSを活用した監視効果
- インスタグラムに読書している様子を投稿
- グループチャットで活動報告をする
- Xで進捗を定期的にシェア
これらの方法で、フォロワーや友人たちに自然と見守ってもらえる環境を作ることができます。
監視効果が働く心理メカニズム
人は他者の目を意識すると、一貫性を保とうとする心理が働きます。これを「コミットメント効果」と呼びます。宣言した以上は実行しなければという気持ちが、習慣継続の原動力となるのです
戦略2:誰かのために行動する
「人のため」が生み出す不思議な力
「人のため」に行う行動は、不思議と気力が湧いてくるものです。
こんな経験はありませんか?
ただダラダラと筋トレするよりも、「愛する〇〇ちゃんを守るために筋トレする」方がやる気が湧いてきますよね。「毎日やらなきゃ!」という気持ちが自然と生まれます。
習慣化への応用方法
この法則を習慣にも導入してみましょう。すべての習慣に取り入れるのは難しいかもしれませんが、もし自分の行動が誰かに「GIVE」できるとしたらどうでしょう?
そういう視点で自分の行動を振り返ってみてください。
実践例:読書習慣の場合
私の実体験をご紹介します。友達とご飯に行ったり、家族と話したりする際、その人たちに自分がインプットしたことを教えるために読書をしています。
これは単なる考えではなく、実際に実践している方法です。(知識をひけらかしているように見えないよう気をつけていますが...)
「人のための読書」の3つのメリット
1. インプット効率の向上
人に教えるつもりで読むことで、より深く理解しようとする意識が働きます。
2. 自然なモチベーション
疲れていても「本を読もう!」という気持ちが自然と湧いてきます。
3. 人間関係の向上
「本を読む→教える」を繰り返すうちに、困ったら相談しようと思ってもらえたり、「またあの人の話を聞きたい」と思ってもらえるかもしれません。
「誰かのための習慣」を見つけよう
習慣化で挫折してしまう多くの人は、「自分だけのため」に頑張ろうとしています。しかし、人は本来、誰かのために行動する時により大きな力を発揮できる生き物なのです。
あなたの習慣が誰かの役に立つとしたら、どんな形になるでしょうか?
- 運動習慣 → 家族の健康意識を高めるため
- 読書習慣 → 友人に良い情報を提供するため
- 早起き習慣 → 家族に良い影響を与えるため
- 料理習慣 → 大切な人においしい食事を提供するため
可能性は無限大です。
まとめ
- 環境の力:属するグループがあなたの習慣を決める。人付き合いを見つめ直そう
- 監視効果:家族やSNSを活用した間接的な監視で継続力がアップ
- コミットメント効果:宣言することで一貫性を保とうとする心理が働く
- 利他の習慣:誰かのために行動すると自然にやる気が湧く
- GIVEの実践:すべての習慣に「誰かのため」の要素を取り入れることが重要
習慣化は一人で頑張るものではなく、人との「つながり」の中で育むもの!
今日から、あなたの習慣に「人の力」を活用する要素を取り入れてみませんか?きっと今まで続かなかった習慣も、驚くほど自然に継続できるようになるはずです。